*この記事は2025年度までの情報に基づいています
専門科目について
東北大学の専門科目は熱力学、流体力学、材料力学、機械力学、制御工学の5つの分野から2つの分野を選択する形式となっています。私の周りでは、比較的点数が取りやすいとされている、流体力学、機械力学、制御工学から選択している人が多いと感じました。今回は私の経験を元に流体力学と制御工学について説明していきます。
流体力学
流体力学は、機械系の院試でもっとも簡単と言われることが多い一方で、高得点を取るのも難しいとされています。ここでは、頻出事項について解説していきます。まず、毎年1題出ているのが、二次元ポテンシャル流れです。この問題では、複素速度ポテンシャルが与えられ、そこから速度ポテンシャルと流れ関数を求め、そこから半径方向速度や周方向速度を求め、よどみ点を求めてから最後に流線を書かせるというのが王道になっています。そのほかにもポテンシャル流れに絡めて、連続の式や渦度の式、循環の定義などを確かめる問題が出てきています。基本的には、過去問で出てきたこと以上のことは出てこない傾向にあるので、過去問を使って勉強を行うと良いでしょう。2題目のパターンとしては大きく分けて2種類の問題があります。1つ目が、管路内の流れです。管路内の流れで大切なのが、ベルヌーイの定理と連続の式についての正確な知識です。どのような場面では、ベルヌーイの定理や連続の式が使えてどの場面では使えないのかそれぞれの定義から勉強すると正確に解くことができるでしょう。2つ目に、速度分布や速度に関する方程式が与えられた状態で、速度を求めたり、流量を求めたり、ニュートンの粘性法則に基づいてせん断応力やかかる力を求める問題です。このような問題では、それぞれの力の定義をしっかりと把握することでトリッキーな問題が出てきても臨機応変に対応することができると思います。そのほかにも、運動量保存則やレイノルズ数についての定義を問う問題もよく出題されるので勉強しておきましょう。
制御工学
ここからは制御工学について解説していきます。制御工学は大きくわけて古典制御と現代制御にわけることができ、それぞれ一題ずつの出題となっています。高度な数学的な知識は不要な一方で、パターンはかなり限られてくるので、わかる問題を落とさないことが攻略の鍵となるでしょう。まず古典制御につてですが、もっともよく出てくる問題がフィードバック制御の問題です。フィードバック制御における伝達関数や入力関数から出力を求めるという問題や根軌跡、ベクトル軌跡、ボード線図を書かせる問題が主に出題されています。また、伝達関数やベクトル軌跡などから安定性を解析する問題もよく出てきています。古典制御は現代制御に比べ問題の範囲が少ないので勉強していけば解けると思います。次に、現代制御について見ていきます。現代制御でよく出てくるのは極配置法を利用した設計です。そして、システムの可制御性、可観測性の判定と、そこからオブザーバを設計する問題です。しかし、現代制御はさまざまな問題が考えられるため、対策が難しくなっています。私の考えでは、過去問を15年ほど行うことでほとんどのパターンを勉強することができると思います。
最後に
ここまでは、東北大学工学研究科専門科目について話してきました。専門科目は差がつきにくい一方で、大学院合格に向けては6割ほどの点数を取る必要があるため、しっかりと勉強していくことが求められます。しっかりと勉強することで合格が近づくので、最後まで諦めずに勉強していきましょう。
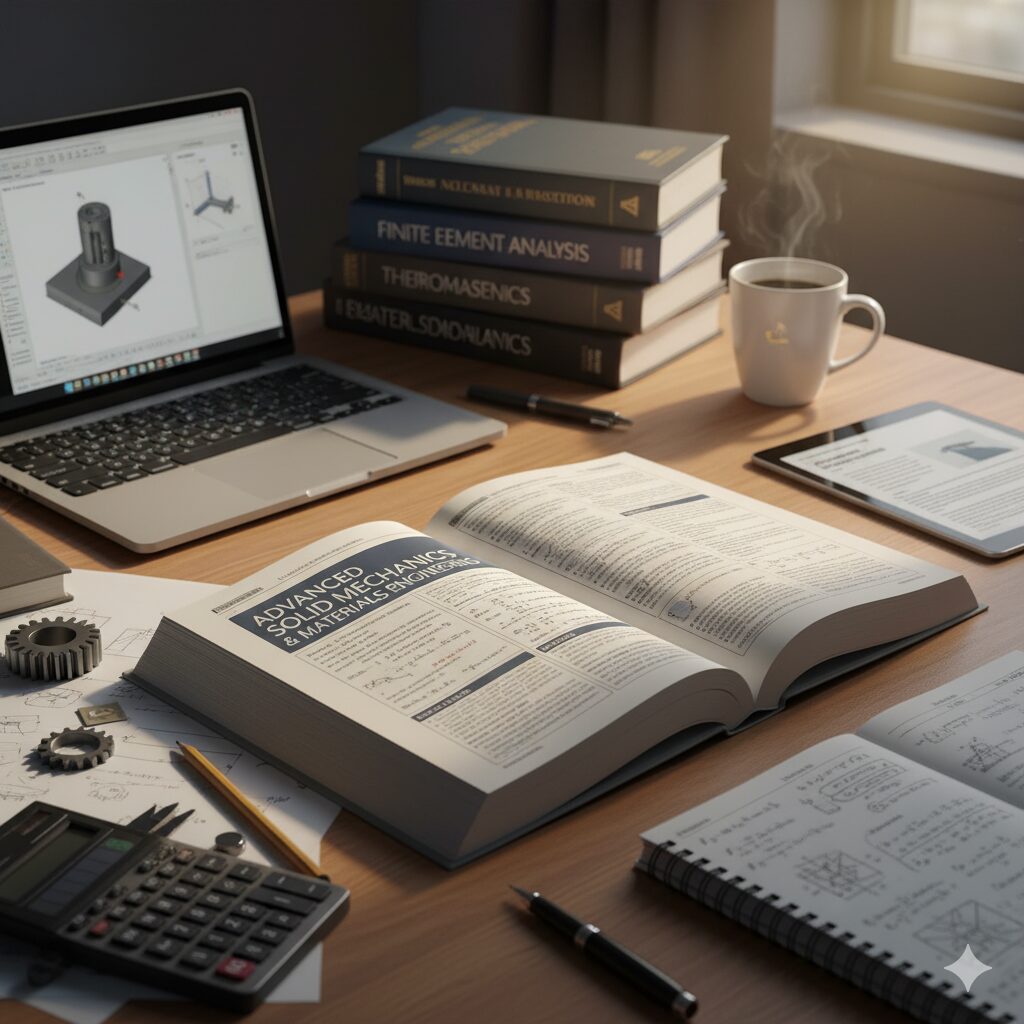

コメント